エレキギターとベースのネックジョイントの違い | THEONE | ハイエンド エフェクターなどの解説
ネックとボディ2つを繋ぐ ネックジョイント 方法によるそれぞれ特徴は?
エレキギター・ベースはネック部分とボディ部分に分かれており、この2つを結合することを ネックジョイントと呼ばれ、現在では結合の仕方によって『セットネック』、『ボルトオン』、『スルーネック』3種類に分類されます。
木材でネック、ボディを構成されるギターは、選択された材によってサウンド面も含めてそれぞれの特徴があります。
ある程度のキャリアを積んだプレイヤーであればエレキギター・ベースでもネック材、指板材、ボディ材によるサウンドの傾向をある程度の把握している方も多いと思いますが、これらネック、ボディがどのような ネックジョイント の形式、接合するフレット位置、ジョイント部の面積、長さ、加工精度によって製作されているのかもサウンド面に大きく影響すると言えます。また、それぞれの構造、工法の違いによってサウンド面以外にも演奏性、メンテナンス性にも違いが生じます。
『セットネック』、『ボルトオン』、『スルーネック』それぞれの特徴をサウンド面、構造などを細かく説明していきたいと思います。

セットネック
Gibsonに代表されるセットネックジョイントは、古来よりクラシックギター、ヴァイオリンなどで採用されている弦楽器の伝統的な工法です。厳密には、ダブテイルジョイント工法と呼ばれ、ソリッドギターが登場する1950年前後からのセットネック工法とは若干異なります。
日本では蟻溝継ぎ工法と呼ばれ釘などを使わない古来からある木材を継ぐ技法であり、現在でも宮大工などが使う伝統工法です。ダブテイルジョイントは、ボディ側が凹、ネック側が凸の形になっており、鳩の尻尾の形のように上部の幅が狭く、下部の幅が広いために、凹と凸を組み合わせると動かない仕組みになっています。
エレキギター(ソリッドギター)でのセットネックジョイントは1952年Gibsonレスポールの発売で採用されたボックスジョイントと呼ばれるセットネックです。Gibsonは以前からフラットトップやアーチドトップモデルをダブテイルジョイントで製造しており、この工法をレスポールでは、ネックの凸部分をボックス形状にして、ソリッドであるボディの一部分に凹部分を設けて接着しました。ネック側の凸部分はダブテイル形状ではないのでボディとのホールド力はそれほど高くないとも言えますが、凸部分(中子・テノン)がフロントピックアップ下部まで達しており、十分な強度と音響伝達性を確保されました。その後Gibsonのソリッドタイプでは、ほぼ全てのモデルでこのセットネックジョイントが採用されて現在に至ります。(中子・テノン部分の大きさはモデルによって違いがありますが)
このような構造上、ネックとボディの密着度がボルトオンジョイントに比べて高く振動伝達性においてはアドバンテージ有り、本体の鳴り、サスティーン面のおいて有利とされます。
SGなどでみられるようにジョイント部の接着後にある程度の加工が比較的容易(スルーネックジョイント程ではありませんが)で高音域・ハイポジションでの演奏性は優れてます。また、接着によって接合されているのでボルトオンに見られる外的な衝撃によりネックが接合部で動く『センターズレ』などもありません。
ただし、ボルトオンネックジョイントのようにネック、ボディを別々に作業して後に組み込むことは出来ず、比較的早い段階でボディとネックを接着する必要があり、塗装などを含めて作業効率が良いとは言えず、完成までの時間も要します。また、ネックにトラブルが生じた際にもボルトオンのように外しての作業は出来ず、ましてや分解が生じる場合などでは、きわめてハードルは高くなります。しかしながら、レスポールに代表されるセットネックジョイントは、この構造がもたらす音がエレキギターサウンドの1つのキャラクターとして定着している伝統的なネックジョイント方法です。
ボルトオン(デタッチャブルネック)
ボルトオンネックジョイントは、実質的に世界初のソリッドタイプエレキギター(1948年)を作り出したFender社が採用したネックジョイント方法です。それ以前のギターは、弦楽器では一般的なダブテイルジョイントによるセットネック工法でしたが、ソリッドボディにネックジョイントのためのポケットを設けて、接着するのではなくネックの底部をボルトによって接合する方式を採用しました。それまでダブテイルジョイントでギターを製造していたGibson ,Martin、Epiphoneなど各社には、この斬新な発想は考えが及ばなかったと思います。(Fenderがそれ以前はラップスティールなどを製造していた事が、この発想に関わっていたとされます)
ネックプレートを介して結合部は接着と同等の十分な強度を確保されており、ネック・ボディを別々に最小工程まで製作を進められることで生産効率を向上され、低いコストでの生産が可能です。
ストラト、テレキャスターに代表されるほぼ全てのFender社のギターで採用されるジョイント法で、現在でも最もポピュラーなネックジョイントの1つで、様々なブランドで採用されています。
現在では、各社モデルによってボルトの数はさまざまですが、Fenderのようなプレートを介した4点止めがおそらく一番多いと思います。理屈だけで言えば、ボルトの数が多い方が締めつける力を分散できるので、全体としてより強い力で締めつけることができます。結果としてネックとボディの密着度が増すので、振動のロスが少なくなり、サスティーンも良くなるということになるのでしょうが、多ければ良いというものではなくネック、ボディ双方に穴をあけすぎることになり、木材自体の強度が低下してしまい、トラブルの原因になる恐れがあります。
そのあたりは使用されている木材の強度とのバランスも重要になってくるかと思います。サスティーンに関しては、他のジョイント方法に比べて比較的短めな傾向にあると言われていますが、これは一概には言い切れないと思います。ジョイント部のネック底面とボディのポケット部を丁寧に仕上げられているボルトオンジョイントであれば、十分なサスティーンを得ることも可能でしょう。
量産されている安価なボルトオンジョイントの楽器には、ネックポケット部にボディの塗料などが入り込んでネックと接地部分の精度に難がある状態などによって、ネックとボディがしっかりと密着せずに、振動のロスが大きくなり、『ボルトオン=サスティーンが弱い』とイメージを抱かれてしまう要因です。
ボルトオンジョイントを採用するギター最大のメリットは、メンテナンス性の高さです。ネックとボディの取り外しが可能なので、ネック廻りの修理などで作業効率が格段に良い事です。ネックの仕込み角度を調整したり、センターズレの補修やネック交換など、ネックが簡単にボディから外せることの恩恵が多々あり、エレキギターでは、最も多く採用されるネックジョイントであります。
スルーネック(Neck Through Body)
スルーネックとは、ネック材のエンド部がボディの一部分としてボディエンド部まであり、ウイングと呼ばれるボディ材で両側から挟みこむように接着してボディ部分を構成する構造で、ネックとボディを結合するいわゆるジョイント部は存在しません。セットネック、ボルトオンに比べて新しい工法で、1963年にGibsonが初めてFirebird、Thunderbird bassで採用しました。(初期のリバースモデル)
ネック材がボディエンド部まで貫くことになり、非常に長くなってしまうため、1ピース構造のネックでは反りや歪みを起こしやすく、3~7ピースほどの複数の木材を貼り合わせてネック部分を構成するのが一般的です。
音の伸びが良い豊かなサスティーンが得られるといった点がスルーネックのメリットとして一番よくあげられるのではないでしょうか。ネックがボディのセンター部分を貫く構造上、弦の支点となるナットとブリッジがネック材部分の上にあるので、理屈の上では振動伝達性が他のジョイント方法より最も優れておりサスティーン面ではアドバンテージが有ると言われます。また、ハイポジションでの演奏性は最も優れているといった点もメリットとしてよくあげられます。セットネックやボルトオンの場合、強度面を考慮するとネックとボディを接合するための接着面やボルトで固定するためのスペースがある程度必要になります。多少のジョイントヒール部分の加工は可能ですが限界があります。
そもそも、スルーネックはジョイントヒール部分が無いので加工の自由度が高く、ハイポジションであってもスムーズなフィンガリングを可能なので、他のジョイント方法に比べスルーネックは演奏性に優れていると言われるのです。
スルーネックは、音質面や演奏性などさまざまなメリットがあるのですが、生産効率性、メンテナンス性に優れずセットネックやボルトオンに比べ普及していません。
ボディとネックを別々の工程で製造できるボルトオンはもとより、セットネックも塗装前まではネックとボディの接着段階までは別々に製造することが可能です。
しかしスルーネックでは最初ネック工程から常にボディエンドまでの長さで作業を行い、その後ウイング部を取り付けてのボディの工程で、常に完成時の全長がある状態での作業になり、極めて生産性が悪いと言えます。
しかも先述の通りネック材は数ピースの長い木材を使うため、事前にプライウッドにしてシーズニングをする必要があり、何かと製作工程が多く製造コストも高くなり、結果として高価格なハイエンドモデルに採用することが多い仕様と言えます。また、ネック材には強度を確保されるメイプルなどの硬質な木材を中心にプライウッド材で製作することが多いのですが、どうしても高音域寄りの硬めな音質になる傾向があり、ギターよりベースに採用される傾向に現在はあります。
エレキギター・ベースを代表するモデルは ネックジョイント 方法の違いによってもサウンド特性は決定される
セットネックやスルーネックなどのコストがかかる ネックジョイント 方法がギター工学的には良いとされますが、現在では、プレイヤーが感じる音の良し悪しにも幅が生まれており、またプレイヤビリティ面でも新たな改良が加えられるなど、ネックのジョイント方法によって良し悪しを決めることは殆どなくなっていると思います。
現実的にストラトやレスポールをスルーネック構造で製作したとしても、もはやそれぞれのサウンドキャラクターとかけ離れてしまいます。「どんな音をだしたいか」、「どんなプレイスタイルか」などで楽器を選択されるケースの方が増えてきております。新たなギター・ベースを手に入れる際、1つのファクターとして ネックジョイント 方法によるサウンド特性、プレイアビリティの違いを参考にしていただければと思います。
Theoneストアのご案内
Theoneストアでは本店、Yahoo店、楽天市場店の3店舗にて運営しています。Yahooと楽天につきましては、各種モールのキャンペーンに参加していますので、お得にポイントをゲットできる日も御座いますので、モールユーザー様は是非ご利用ください。
好評頂いている DYNAX IR に関しましては 本店のみの取扱いとなります。
最新投稿記事
-

アンプシミュレーターIR で音が激変する! DYNAX IR を考察
-

全機種比較| ギターエフェクター 初心者におすすめ エフェクツベーカリー の全て!現役プロが教える選び方のコツ
-

ギターアンプ パワー菅 選び方から交換方法、バイアス調整のことなどプロが徹底解説
-

Strymonエフェクター 定番モデルとサウンド品質を徹底比較!ギタリストにおすすめはこれだ
-

ギターアンプ プリ菅 12AX7 交換で音質激変!理想のサウンドを手に入れる方法
-

新時代の リバーブペダル Strymon BigSky MX
-

RETROLABピックアップ は、最高峰の ストラトピックアップ だと思います!
-

VERTEX SSS ダンブル系プリアンプは 掛けっぱなしが基本!
-

VELVET COMP VLC-1 を modしてみた DYNAX mod
-

Marshallアンプ では 初のコンボアンプ 1962 Bluesbreaker
-

近代Marshallサウンドの方向性を決定づけた JCM800 シリーズのキャビネット1960A
-
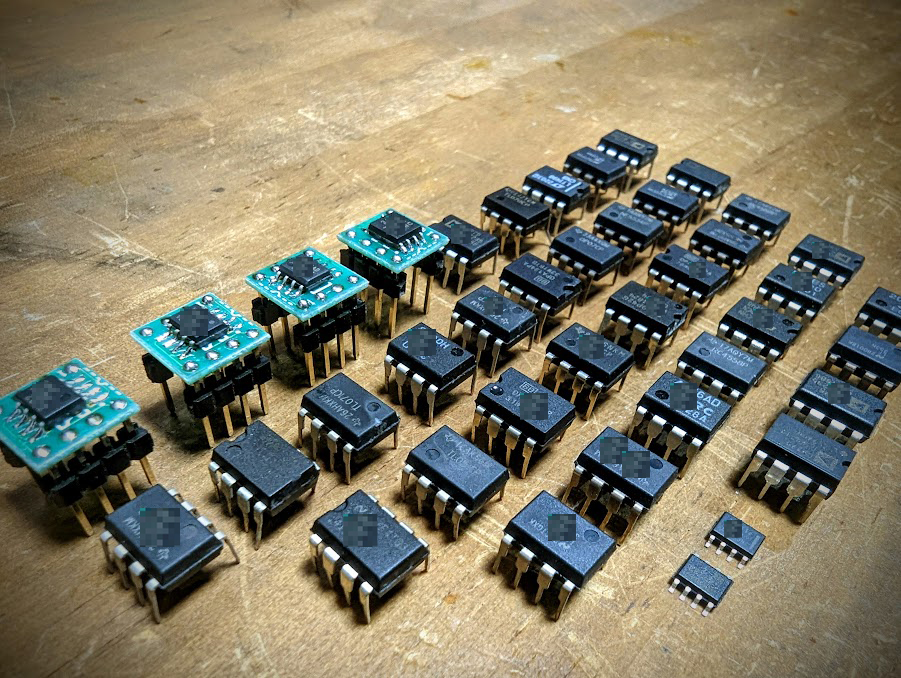
DYNAXオーバードライブ 開発開始しています。


