ギターの塗装 とその特徴 | THEONE | ハイエンド エフェクターなどの解説
サウンドにも影響を与える ギターの塗装 その目的、種類は?
ギターの塗装 は、他の木工製品同様に木材の保護と美観(ルックス)の生成・維持を目的として施されています。
また、一般的には意外と知られていませんが『音のまとまりをつくる』効果がある言えます。
アコースティックギターはもちろんですがエレギギターも弦の振動だけでなく、本体自体の振動によっても音色が変わってきます。そのため、塗装をするかしないかでギター本体の振動の仕方も変わってくるのです。実際に全く塗装をしていないギターを弾いてみると、非常に良く鳴っていと感じるのですが、ネック、ボディなどが過度に振動して音のまとまりがない感覚ですかね。
ギターは塗装を施すことにより適度に振動が抑えられ、ネック、指板、ボディなどのそれぞれ違った木材の振動を上手くまとめてくれると言えます。
しかしながら、厚すぎる塗装は楽器本来の自然な鳴りを損ないます。ギターの塗装 は、一般的にポリエステル、ポリウレタン、ラッカーなどが一般的です。それぞれの特徴とサウンドへの影響を理解しましょう。
画像引用: https://guitarhana.info/2017/03/31/post-716/

ポリ塗装 ポリエステルとポリウレタンは違う
「ポリ塗装」と呼ばれるものにはポリウレタン塗装とポリエステル塗装とがあり、この二種類はどちらも、2つの液を混ぜた反応による硬化で塗膜を形成するので、ポリ塗装としてひとくくりに言われることが多いのですが、ポリ塗装はポリエステルのことで、ポリウレタンとは異なる特徴を持っている。
ポリエステル塗装は、ポリエステル樹脂に汎用促進用の薬剤を添加した主剤に硬化剤を混合して使用します。ポリエステル塗料の特徴は、塗料全体で塗膜を形成するので、非常に厚い塗膜が一回の塗布で可能になります。
また、塗膜は表面からの乾燥ではなく内部からの硬化していくため上乾きの心配はありません。数時間から半日もあれば完全硬化し、無溶剤が使われるのでラッカー塗装などに見られる目瘦せもなく、硬化後はプラスティックと同等に硬くなります。塗膜の保護力は優れており経年変化はほとんどありませんが、塗膜に厚みがあるため柔軟性や密着性が低く、硬すぎる故に、強い衝撃が加わると亀裂が入ったり塗膜がパックリと剝れ欠け落ちます。ポリウレタン、ラッカーなどと比較するとポリエステルの方が断然に硬化が速く、一回の塗布で肉厚な塗膜を形成でき、手間と時間が節約できるため、大量生産に向いており、コストも低く主に廉価版などの量産品ギターに用いられことが多いです。
しかし、厚い塗膜は、ギターの鳴りである木工部分の振動を過度に吸収してしまいます。
ポリウレタン塗装はポリエステル塗装と同様に主剤に硬化剤を混合して使用します。ポリウレタンの場合、混ぜた合わせた塗料に溶剤(シンナー)で希釈して粘度を整え、スプレーガンで吹き付けます。溶剤を使用するのでポリエステルのように一度の吹付で肉厚な塗膜を形成することは出来ません。しかしながら、肉厚にならない塗膜を形成できるので、サウンド面ではポリエステル塗装よりアドバンテージが有ると言えます。
短所としては、ポリエステルに比べて硬化時間が遅く、更に塗膜にある程度肉厚を持たせるには数回の吹付が必要で生産性は劣ります。また、ラッカー、ポリエステルに比べて分子レベルでは硬度が劣り、同じ塗膜の厚さであれば音の伝達性に関しては若干劣ると言えるのですが、これらの特性などを総合的に考えるとポリエステル塗装とラッカー塗装の中間的な位置付けになるのではないかと思います
ギターの塗装 に於いては崇拝されるラッカー神話
ギターの塗装 に使われるラッカーとは正式にはニトロセルロースラッカーを指します。楽器業界ではラッカー塗装といえばニトロセルロースラッカーが当然であり厳密に考える必要はないと思います。
ニトロセルロースラッカー(硝化綿ラッカー)とは、植物由来のセルロースに樹脂可塑剤などを配合してニトロ化したものを原料にしたラッカーを指して合成樹脂を原料としたアクリル系ラッカーなどとは区別します。
このニトロセルロースラッカー塗料をさらに有機溶剤(シンナーなど)で希釈し吹き付けますが、乾燥過程は揮発性乾燥であり、含まれていた有機溶剤が揮発した後にニトロセルロース固形分が残り塗膜を形成されます。故に、一度の吹付で塗れる塗膜厚は非常に薄く、何度も塗る重ねる必要があり、乾燥にかかる時間も含めて生産性は低いと言えます。
また、高温多湿な作業環境では塗膜が白化するなど非常にデリケートな塗料です。一度の吹付で形成される塗膜が薄いということは、ポリ系塗料のように削ぎ落とす必要が無く、薄い塗膜を最終的に形成することが容易であるとも言えます。
「ポリ系の方が塗膜は硬い」と言われますが、厚い塗膜がその硬度を生んでおり、そのように言われる理由でしょう。ラッカーは分子レベルでは硬く、薄い塗膜形成が可能であり、振動伝達性が良好でギターのサウンド面においては最も恩恵がある塗装でしょう。
ラッカー塗装は、完成後もゆっくりと溶剤が揮発し続けて、縮みやひび割れ(ウェザーチェック、クラッキング)が生じて絶えずその風合いを変化させる特性がヴィンテージ楽器の魅力の一つとされます。現在では、その風合いを人工的に再現したエイジド加工やレリック加工などは、ラッカー塗装だから可能な加工です。
GibsonやFenderは本格的なギターの製造当初からラッカー塗料を使っていました。ニトロセルロースラッカーは1920年ごろに開発、販売され、それは主に「自動車」の塗装に使われていました。1923年にGMがニトロセルロースラッカーを一番最初に使ったとのことです。デュポン社製(フェンダーも50年代からデュポン社の塗料を使用)現在のように、「どんな塗料がギターにはいいのか?」なんて選択肢が有ったわけではなく、最新で最良とされた塗料がたまたまニトロセルロースラッカーだったのでしょう。その後1950年代後半にかけてポリ系の塗料が開発されFenderでは1968年前後から下地にポリ系の塗料を採用しました。(シックスキンフィニッシュと呼ばれ下地はポリ系の塗料、カラー、トップコート部はラッカー塗装)当時はまだ、塗装によるサウンド面の影響などは考えてなかったのでしょう。
ラッカーは確かに楽器にいいのでしょうが・・・現代のポリウレタン塗装も
1970年代後半に「オールドギター、ヴィンテージ」という新たな価値感が生まれ、現行モデルとの各部ディテールの違いに着目される中で塗装もその一つであり「ラッカー塗装」を崇拝にも近い風潮が生まれたと言えます。
ラッカー塗装の音が良いとされるのは、ラッカーが硬めで厚塗りされない塗料だからと考えられます。
現在では、ポリウレタン塗装も環境に合わせた多様な種類があり、数十年前のイメージとは作業性も格段に違い、ラッカー塗料クラスの薄い塗膜に仕上げることが可能な技術者もおり、殆ど遜色ありません。同等の塗膜厚では、硬度がまさるラッカーの方が振動伝達性においては若干の分がありますが、ギター・ベース木工部とのパッケージにもよっては、ポリウレタン塗料で薄い塗膜に仕上げることが向いている場合もある有るようです。
ハイエンドベースブランドなどでは、銘木での木工製作が多く暴れすぎる「音をまとめる」のに向いている場合もあるようです。このように、出音への影響はそれぞれの特徴がありますが、保護、保管、メンテナンスなどの仕方も異なりますので、ご自身にとってどの点を重視するかで変わってきます。レリック加工が施されたルックスのギターが欲しい方は、出音への影響うんぬん以前にラッカー塗装になります。冒頭でも述べてように ギターの塗装 は、第一に木材の保護と美観(ルックス)の生成・維持であります。更にそれぞれの塗装による影響を理解することでギターへの造詣が深まると思います。
Theoneストアのご案内
Theoneストアでは本店、Yahoo店、楽天市場店の3店舗にて運営しています。Yahooと楽天につきましては、各種モールのキャンペーンに参加していますので、お得にポイントをゲットできる日も御座いますので、モールユーザー様は是非ご利用ください。
好評頂いている DYNAX IR に関しましては 本店のみの取扱いとなります。
最新投稿記事
-

アンプシミュレーターIR で音が激変する! DYNAX IR を考察
-

全機種比較| ギターエフェクター 初心者におすすめ エフェクツベーカリー の全て!現役プロが教える選び方のコツ
-

ギターアンプ パワー菅 選び方から交換方法、バイアス調整のことなどプロが徹底解説
-

Strymonエフェクター 定番モデルとサウンド品質を徹底比較!ギタリストにおすすめはこれだ
-

ギターアンプ プリ菅 12AX7 交換で音質激変!理想のサウンドを手に入れる方法
-

新時代の リバーブペダル Strymon BigSky MX
-

RETROLABピックアップ は、最高峰の ストラトピックアップ だと思います!
-

VERTEX SSS ダンブル系プリアンプは 掛けっぱなしが基本!
-

VELVET COMP VLC-1 を modしてみた DYNAX mod
-

Marshallアンプ では 初のコンボアンプ 1962 Bluesbreaker
-

近代Marshallサウンドの方向性を決定づけた JCM800 シリーズのキャビネット1960A
-
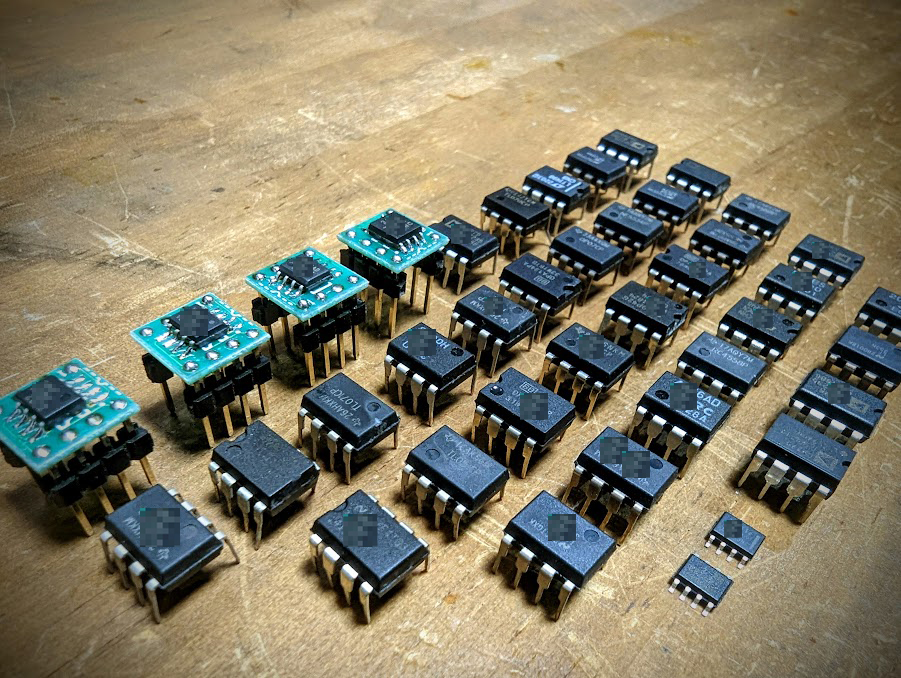
DYNAXオーバードライブ 開発開始しています。


