ギターのナットは弦楽器の要 | THEONE | ハイエンド エフェクターなどの解説
弦楽器の要であるギター・ベースの ナット とは?
そもそも ナット とは、ヘッド部分とフィンガーボードの境目にあるパーツです。クラッシック楽器のヴァイオリンなども含め、すべての弦楽器は、その構造上、弦振動の支点をブリッジサドルと ナット が担っています。弦の一方がブリッジ(ブリッジサドル)などで固定されて、もう一方は糸巻き(ペグ)により巻かれ ナット によって支えられているのです。皆さんがギターをチョイスする際に、演奏性、音色、ルックスなど、さまざまな要素が有ると思うのですが・・・弦振動を担う、2つの支点となるナット、ブリッジの状態は最も重要で、ギターでは ナット の表面に一定の間隔で6本の溝が彫られ、それぞれ弦の『横ずれを防ぎ、支える』『それぞれの弦間隔を設定』『ストリングポストへスムーズに誘導する』など、ナット は弦振動の支点としての役目以外にも多くの役割が有りブリッジ以上に重要と言え、この小さなパーツ次第で楽器全体のコンディションが大きく左右されると言えるのです。
しかも、このナットの取り付けは、製作工程の最終段階に、職人の手によって行わなければならない作業でありモデルによって整形の仕方や考え方もさまざまです。また、使用される素材は多岐に及び、耐摩耗性、潤滑性、サウンド特性にもそれぞれ特徴があります。今回はエレキギター・ベースにフォーカスして、この ナット について色々と掘り下げて考察していきたいと思います。

振動の支点としてしっかりと弦を支え、横ずれを防ぐ
ヘッド側の支点となる ナット がナットスロットの(ナットが収まる溝)底面部分、指板側面部分と ナット の底面、側面の両方がしっかりネック部と接着し固定することで、正確な弦振動とネック全体の振動を生み出します。ナット部では、もう1つの支点であるブリッジ部との構造の違いで弦を押さえこむプレッシャーが弱く、各弦が収まる溝を造ることで横ずれを防ぎ、チューニングを安定させています。押弦する際は、フレットとサドルの2ヶ所が支点となり音程を決めていますが、この時 ナット が弦を固定しているからこそ、安定した音程を保つことができるのです。
それぞれの弦間隔を設定
通常、弦の間隔を『弦間』と呼び、ブリッジ部での弦の間隔を指すことが一般的で、そのピッチ(間隔)はブリッジ、ピックアップなどである程度決まってますが、ナット側での弦間は、ナット材に溝を切ることでギター製作の最小工程で行います。
ネックの幅、スケール、フレット両サイドの処理の仕方などと、さまざまな要素を加味して決定します。
一概にナット部分のネック幅が同じであっても、ナット溝の間隔は違うことは多々あります。
基本的には1弦、6弦両サイド位置を最初に決めてすべての弦を等間隔にしますが、それぞれの弦の太さは違うので技術者の見解、オーナーの好みなどが反映され、精度が求められる難しい作業です。
その後、張る弦のゲージに合せて専用のヤスリ(ナットファイル)で溝を彫りますが、高さも非常に重要で、高すぎればFなどのセーハコードを押さえるのが難しかったり、開放弦と押弦が混在するC,E,GなどのLowコードでは不協和音になります。また、低く彫り過ぎれば1フレットに接触してビビリが起こってしまい、この場合は修復不可能でやり直しです。
基本となる高さは、各弦の相当するフレット頂点の延長線より若干高くすることになるのですが、張る弦によってのテンションの違いやヘッド形状によってナット部を押さえ込む弦プレッシャーの違いなど考慮する必要があり、技術と経験がいる作業です。
ストリングポストへスムーズに誘導する
ナット の溝でしっかりと弦をホールドする事はナットの大事な役目ですが、チョーキングやトレモロユニットでのアーミングプレイなど音程を変化させる奏法が多用されるエレキギターなどでは、その都度、弦はナット(ブリッジサドルも)上を滑りながら移動しなければなりません。これらの極端な奏法でなくても弦をフレット上で押さえる度に、弦は絶えずナット上で移動を繰り返しており、弦のスムーズな移動を干渉しないナット溝が求められます。
ナット溝の角度、深さ(弦をどの程度ナットの上面から潜らせるか)は技術者の見解によってさまざまです。特に『ナット溝の角度』に関しては、ナット正面から見たストリングポストへ向かう角度と、ナット側面からの角度が有ります。これは、どちらもナットの最も指板側に弦が最初に接する個所であるのは当然なのですが、そこからストリングポストへ向かって2つの角度をどのように設定するのかです。これは各製造メーカー、技術者、リペアーマン、考え方はさまざまで定説となるような見解は現状ないと言えます。

ナット の種類、材質、その特徴は?
ナットで使用される素材は多岐に及び、耐摩耗性、潤滑性など、それぞれで特徴があり性能を左右します。更にプレイヤー自身によるサウンドの好みも加味されますので一概にどれがいいとは言えず奥の深いです。エレキギター・ベースでのナット素材の種類とその特徴を紹介していきたいと思います。
*ボーンナット(牛骨)
牛骨はプラスチックと並んで最もポピュラーな素材でありナット交換においても、最初に候補として挙げられるナット材です。その名の通り牛の骨から作られており、なめらかなサスティーンと自然な響きが特徴で、加工性、コスト面も含めてもっとも標準的な材質と言っていいでしょう。ブリーチで真っ白にした「漂白牛骨ナット」、漂白処理していない薄い飴色の「無漂白牛骨ナット」、オイルを染み込ませた「オイル漬けナット」の3種類が一般的です。
牛骨にオイルを含侵させて、ナット溝部分で弦との摩擦抵抗を軽減させ、チューニングの安定性を向上させる目的とした処理が施されています。多少の硬度変化が有り、サウンドは若干マイルドな響きになる印象です。
*プラスチック
プラスチックナットはギター・ベースで最も多くナットに使用されている素材で1万円程度の安価なギターから数十万円する高級モデルまで、幅広く採用されています。何と言ってもプラスチックは安く加工が容易で、コスト面では圧倒的な有利性が有り、特に低価格帯のギター・ベースで積極的に用いられ、素材による構造的なむらが無いので安定した比較的軽いサウンドの印象です。しかしながら、耐久性では他のナット材には劣り消耗も早いです。製造段階であらかじめ弦溝が切られており、それぞれのギター・ベースに合せての溝切を行っておらず、ナットの本来の目的においての精度に関しては低いと言わざるを得ません。
*象牙
象牙は古くからクラシック楽器で ナット として使われ、日本では印鑑の素材や工芸品として珍重されてきた素材で、現在では自然保護の観点からワシントン条約のもと取引が厳しく制限されており入手するのが困難で高額な素材ですが、今日でも一部のハイエンドなアコースティックギターやクラシックギターに採用されています。象牙は牛骨より硬く、音響特性としては美しい高域と輪郭を備えてサスティーンも有り、天然素材のならではの自然な響きを持つ、最高級のナット材とされます。
*ブラス
ブラス(真鍮)は音の伝導が最も良い金属であり、金管楽器に多く使われます。1970年代後半からエレキギター・ベースに使われ始めました。金属製なのでナット材の中ではフレットの特性と最も近く、開放弦とフレット上を押弦の音質差が少ないと言えます。一般的にイメージされるほど極端に金属的な音ではなく、アタック感やサスティーンに関しては最もアドバンテージが有ると言え、現在では特にハイエンドブランドのエレキベースに使われことが多いです。デメリット点は、牛骨などのナット材に比べて加工、整形が難しく、使う工具の消耗も早くなり、素材の価格も含めて作業工賃は高めになります。また、最終仕上げ後のブラスは金色で美しい輝きを放っていますが、経年変化で黒ずんできたり、果ては腐食して緑青出てしまったりして定期的に磨く必要が有ります。
著者の個人的な見解ですが、エレキギターよりは、エレキベースの奏でる帯域にブラスナットの特性はマッチしてると思います。
*カーボン・グラファイト
カーボン・グラファイト共に、炭素を原料とする物質で航空機、釣り竿、ギター・ベースのネックにも使われる素材です。グラファイトの方が炭素の純度は高く、高圧を加えるとダイヤモンドが出来ることはよく知られていると思います。当然、耐久性が高く潤滑性もあり、高域に丸みのある、輪郭のはっきりしたサウンド特性とされます。しかし、耐久性が高いことがもろ刃の剣と言え、加工は難儀で工賃は高い傾向にあります。
*TUSQ
TUSQ(タスク)は、米国グラフテック社が開発した人工象牙です。個体差なく加工性は良好、倍音が豊かでサスティンも良く、象牙に比肩するサウンドと言われアコースティックギターのサドルなどにも使われています。牛骨に次いで支持を集める素材ですが、消耗が早いことがデメリットとされます。
タスクXLとブラックタスクは、PTFE(テフロン)を含有した高分子素材で、弦振動によりテフロン粒子が放出されることで摩擦が軽減されスムーズな弦を可能にし、チューニングの安定性を図っているとされます。
*ロックナット
フロイドローズタイプのトレモロが搭載されているギターに付いているナット部分のパーツです。
ブリッジ部とナット部で弦をロックする構造のフロイドローズタイプは激しいアーミングプレイでもチューニングが狂いにくいのが最大のメリットです。ロック式のナットは鉄製がほとんどで重量もありサスティンをかなり稼ぐ事ができますが、フロイドローズタイプのトレモロユニットの一部分であり、ナット交換などの選択肢にはなりません。その構造上の特性か冷たいサウンドと言われます。。
*ローラーナット
ローラー(ベアリング)が内蔵された金属製のナットで、弦がベアリング上に乗ることによって摩擦が低減され、チューニングの安定性やサスティーンの向上といった効果が得られる。チョーキングやアミーングで弦が動く際にローラーが追従して動く構造となっており、ジェフ・ベックモデルのストラトで採用されていることで知られるナット部のパーツです。通常の ナット からローラーナットに付け替えるためには、設置部分になるナットスロットをブリッジ側に削る加工が必要で、一般的なナット交換とは異なり、再度通常の ナット に戻すことを基本的に視野に入れない改造の部類になると思います。
ナットはギター・ベースのパーツで随一の消耗品
エレキギター・ベースではポット、ジャックなども電気パーツも消耗の激しい部品ですが、エレクトリック、アコースティックに関わらず最も消耗の早いパーツにナットが挙げられます。ナット が消耗していなくてもデフォルトの状態では、溝の高さなどが万人に対応可能な仕上げになっており、専門の技術者に調整を依頼することで演奏性が劇的に向上することがあります。ブラスなど金属製以外の ナット は、弦よりも柔らかい素材であり弦振動や押弦時の圧力で徐々に摩耗していきます。(ブラスも摩耗していきますが)
外見上は、それらの変化に気付くことは難しく、不自然なサスティーン、不安定なチューニング、開放弦でのビビリ、等々症状が現れ交換の必要性に迫られることになります。その際に前述した内容を理解しておくことで、技術者と細かな希望や意見交換に役立つと思います。弦楽器において ナット は弦振動の支点になる重要なパーツなのです。
Theoneストアのご案内
Theoneストアでは本店、Yahoo店、楽天市場店の3店舗にて運営しています。Yahooと楽天につきましては、各種モールのキャンペーンに参加していますので、お得にポイントをゲットできる日も御座いますので、モールユーザー様は是非ご利用ください。
好評頂いている DYNAX IR に関しましては 本店のみの取扱いとなります。
最新投稿記事
-

アンプシミュレーターIR で音が激変する! DYNAX IR を考察
-

全機種比較| ギターエフェクター 初心者におすすめ エフェクツベーカリー の全て!現役プロが教える選び方のコツ
-

ギターアンプ パワー菅 選び方から交換方法、バイアス調整のことなどプロが徹底解説
-

Strymonエフェクター 定番モデルとサウンド品質を徹底比較!ギタリストにおすすめはこれだ
-

ギターアンプ プリ菅 12AX7 交換で音質激変!理想のサウンドを手に入れる方法
-

新時代の リバーブペダル Strymon BigSky MX
-

RETROLABピックアップ は、最高峰の ストラトピックアップ だと思います!
-

VERTEX SSS ダンブル系プリアンプは 掛けっぱなしが基本!
-

VELVET COMP VLC-1 を modしてみた DYNAX mod
-

Marshallアンプ では 初のコンボアンプ 1962 Bluesbreaker
-

近代Marshallサウンドの方向性を決定づけた JCM800 シリーズのキャビネット1960A
-
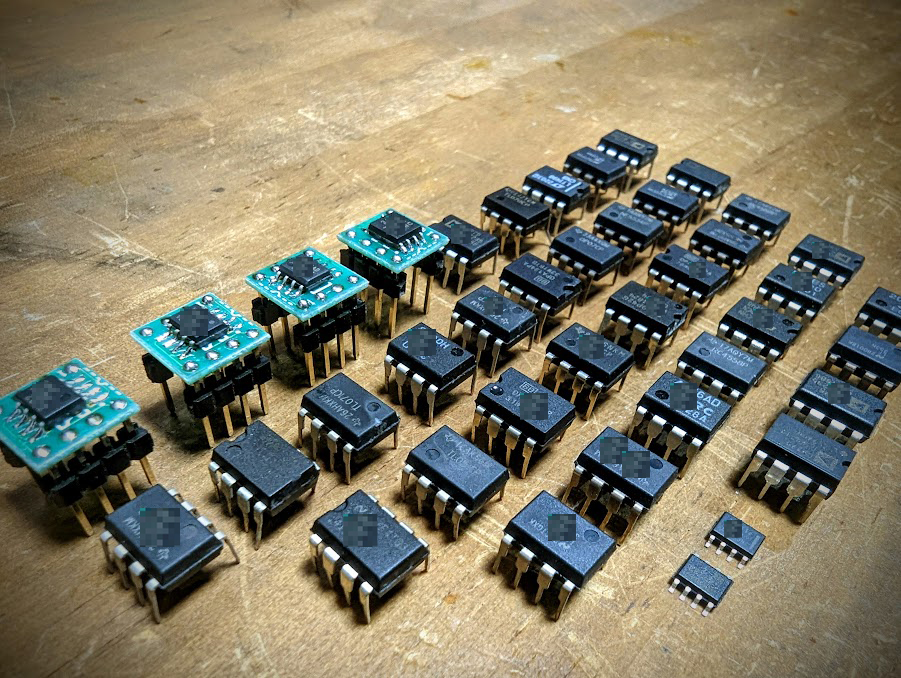
DYNAXオーバードライブ 開発開始しています。


