ストラトキャスターサウンド の特徴を考察 Fender Stratocaster | THEONE | ハイエンド エフェクターなどの解説
Fender Stratocaster のスペック変更に伴うサウンドの変化
Fender Stratocaster に代表されるストラトキャスターサウンド はどのような変化していったのか?
現在では、細かな年式のヴィンテージリイシューモデルがカスタムショップなどからプロデュースされていますが、それぞれ特徴的なスペックを持ち、サウンドキャラクターを形成していると思います。1954年のストラトキャスター誕生からネック、ボディ、ピックアップ、塗装などのスペックチェンジが有り、それぞれ特徴的な ストラトキャスターサウンド を作り出されました。しかし、基本であるメイプルネック、ダブルカッタウェイアルダーorアッシュボディ、シングルコイルピックアップ×3など、現在まで約70年間、変わらぬ仕様です。
製造年代により使用するボディ材、ネックを構成する材質やピックアップ、その他のスペックにも変化があるため、人それぞれに ストラトキャスターサウンド のイメージが異なる要因となっています。今回は、レオ・フェンダー期(一般的に1965前後まで)から、その後のCBS期である80年前後までを中心にスペック変更に関連する ストラトキャスターサウンド を考察していきたいと思います。

ストラトキャスター1954年発売当初~1956年中頃
Telecasterの上位機種として発売されたストラトキャスターは、ダブルカッタウェイのコンターボディを採用し、それまでのエレキギターで一般的であった2ピックアップから3ピックアップを採用することで豊かなサウンドバリエーションを持ち、新たに開発されたビブラートユニット『シンクロナイズドトレモロ』が搭載されTelecasterとは違ったサウンドキャラクターを決定図けたと言えます。
1ピースメイプルネックの特徴的な太くアタック感の強いサウンドとTelecaster同様にアッシュ材が採用されたボディは北米南部産のスワンプアッシュが採用され、クリアーな高音域と力強いローエンドを持つ特徴と相まったブライトでありながら締まった低音域を持ち合わせたサウンドが特徴的です。Telecasterでは、アッシュの美しさ木目を活かしたブロンドカラーでしたが、ストラトでは2トーンのサンバーストが標準カラーとして採用されますが厳選された良質で軽量のスワンプアッシュを採用していることはサンバーストカラーのシースルー部分から確認できます。
ネックシェイプはU~V字型の中間的な太目の感じですが個体差が大きく、特に54年製に関しては試作的な要素が強かったと思われ個体差が大きい印象です。
塗装は、当然ハイソリッドのニトロセルロースラッカーですが、ボディに採用されたアッシュ材が持つ特徴的な太い導管を下地工程で処理する必要が有り、後に採用されるアルダーボディと比べて若干、厚めです。

1956年中頃~1959年中頃
この1956年中頃からボディ材にアルダーを採用し、ネックの形状も57年製に代表されるV字型に、その後スリムなUシェイプと変化していきます。ピックアップなど細かなマイナーチェンジも多少有りますが、この時期のストラトキャスターサウンドを決定づける特徴は、やはりアルダーボディでしょう。
それまでボディに採用していたアッシュ材は、導管の目止めなど下地処理に手間がかかりコスト面から、当時は比較的安価で、加工も容易な北米産のアルダー材に変更されました。アルダーはアッシュに比べて密度のばらつきが少なく、適度な硬さを持ちミドルレンジを中心にフラットでバランスの取れたサウンド特性です。ボディ材の変更によって塗装方法も変更されることになりました。アルダーがアッシュよりも色味が暗く、色の個体差も多く、発色を良くするために脱色する『ブリーチバースト』と呼ばれる塗装工程になります。アルダーはおとなしい杢目ですが、アッシュのような太い導管を処理する工程が無く、塗装は全体的にアッシュボディの時代より薄めの塗膜で、よりボディの鳴りを反映してると言えます。この時期のストラトキャスターは1ピースメイプルネックの持つ太くブライトなアタック感とアルダーボディの豊かなミッドレンジが相まった50年代 ストラトキャスターサウンド を象徴すると言えます。
1959年中頃~1964年中頃
1959年中頃から全てのFenderギターはローズ指板が採用されたことで、そのサウンドは大きく変化します。50年代アルダーボディと同様、ミッドレンジを中心に全ての音域で安定したサウンドを保ちますが、1ピースメイプル期の特徴であるブライトでアタック感の強い特徴は影を潜め、マイルドで粘りがあり奥行を感じます。このローズ指板への変更当初から62年の初期までは『スラブボード』と呼ばれ、ネックバック材のメイプルと指板がフラットに接着され、後のラウンドボードと比較して指板センター部分の厚みは倍以上有ります。「スラブボード期は音が太い!」などと言われてますが・・・著者の印象では、全体的な音の太さの違いは感じず、強いて言えばボルトオンネックジョイント全般で感じるハイポジションでの『音やせ』に関してはスラブボード期の方に分があると感じます。
62年途中から指板接着面が指板Rと同じ7.25で接着されます。この変更に関しては、ローズ、メイプルの収縮率の違いに対応、広い接地面にすることで剛性を高める、トラスロッドナット部の干渉が無く工程の簡略などと諸説ありますが、その工程の難易度を考えるとコスト削減などが理由ではなかったことは確かでしょう。実際、この変更以降から80年代のリイシューモデルモデルが登場するまで採用されました。また、63年~64年に製造された中には比較的肉厚のネックが散見され、サウンドはメイプル部の容積が反映された影響でラウンド指板でありながら非常にファットです。
ローズ指板採用によってトラスロッドのインストール方法も変更されました。1ピースメイプルネックではネックの裏側からトラスロッドスロットを設けていましたが、Gibsonなどでも一般的な指板接着前に挿入する方法になりました。指板部とネック部が別々なら当然この方法を選びますよね。このローズ指板採用とほぼ同時期にピックガードがそれまでの1プライから3プライになります。同時にコントロール周辺部分だけだったシールドプレートが、ピックガード裏全体を覆うタイプに変更されました。ピックガードが1プライか3プライは音との関係は無いでしょうが、このシールドプレートの変更はサウンドに関りが有るように思えるのです。この変更後のシールドプレートは全てのピックアップ周辺まで及んでおり、アルミ製であるシールドプレートは磁性体ではないですが通電性があることで高域が削がれてサウンドへ何らかの影響を及ぼしていると考えられます。ローズ指板、アルダーボディのサウンド特性にこれらも相まってマイルドなアタック感と奥行きを感じる粘りのあるサウンドがこの時代の特徴でしょう。

1964年中頃~1968年初期
この時期のFenderは親会社がCBSへ移行するトランジション期で、様々な仕様が変更されていくことになります。ピックアップはそれまでのブラックボビンならグレーボビンに、ロゴは『スパゲティロゴ』からブランド名を大きくアピールした『トランジションロゴ』へ、指板は『ブラジリアンローズ』から『インディアンローズサウンド』へ、塗料の変更やピックガード材の変更、また66年からCBSフェンダーの象徴とされるラージヘッドの導入など・・・数々のスペックが変更されますことになりましたが、サウンドに関わる変更についてまず挙げられるのは、ピックアップでしょう。
一見して判断の付く、ボビンに使われたバルカンファイバー材の色が変更されますが、同時にコイルのワインディングパターンが変更されています。それまでの搭載されていたブラックボビンピックアップは特徴的なワインディングパターンもあり、豊かな中域から低域が特徴でしたが、グレーボビンは出力こそ同程度ながらワインディングがタイトになり、偏りのないフラットなサウンド特性と言えます。指板材の変更は、ブラジルからの供給されるローズ材のクオリティー低下に損なってインディアンローズへの変更がされました。(同時期にGibson、Martinなど各社もインディアンローズへ移行しています)この変更によってアタック感がよりマイルドになった傾向です。
塗装に関しては引き続きニトロセルロースラッカーですが、販売店でのディスプレイ中などにクラッキングなどの不良発生を懸念して、『リターダー』を添加してのラッカー塗装が行われ、塗膜全体が若干柔らかくなり、サウンドにも影響を与えていると想像されます。また、ヘッド形状の変化による直接的な音への影響は殆ど無いと思われ、むしろこの時期にヘッドの厚みが徐々に増していったことよってテンションに影響を与えています。50年代から同じクルーソンのペグが採用されていますが、一見してストリングポストのヘッド側露出部分が短くなっているので、容易に把握できると思います。ナット部からストリングポストへ向かう弦の角度は緩やかになり、サウンドにも表れています。
著者の主観では、ローズウッドのウエット感を持ちつつも、コードを弾いた時の煌びやかなサウンドを持つ印象です。
1968年中頃~1971年初期
この時期の仕様変更で目を引くのは、トランジションロゴからモダンロゴへの変更で、80年代初期まで続くCBSフェンダーを象徴するデザインですが、最も大きな変更は、下地にポリエステル塗装を導入したことが挙げられます。『シックスキンフィニッシュ』と呼ばれるこの方法は、ラッカーでは手間のかかる下地作業をポリエステルによって簡略化し、着色部、トップコートはラッカーで仕上げる生産効率を重視した工程変更です。
当然、塗膜は厚くなりトーンウッドとしてボディの音響特性は反映し難くなっていきました。アンプ、エフェクターなどの周辺機器の開発などでサウンドのコントロールは充実していく中で、ピックアップはよりフラットなサウンドを求めてターン数を減少させて、出力も抑え気味になりました。また、貼りメイプル指板のモデルもこの時代を象徴するオプションでした。60年代は一貫してローズウッド指板のみがスタンダードスペックでしたが、メイプル指板のサウンドを待望する声にこたえる形で、ローズ指板と同様の工程でメイプル指板をラミネートし、ネックバックにスカンクストライプが無いメイプルネックがオプション生産されました。1ピースメイプルネックネックとは違った独特のサウンド特性であり、メイプル指板の「パキッ」としたアタック感を持ちながらも同時期のローズ指板モデルと同様なマイルド感があり、(Jimi Hendrix、Dave Gilmourなどの使用も)その希少性も相まって人気の仕様です。
1971年後半~70年代末期
この時期には、70年代のストラトを象徴であるブレットトラスロッドアジャストメント、3ボルトネックジョイント、マイクロティルト機構やシンクロナイズドトレモロがダイキャスト製へと変更がされました。ネックも1ピースメイプルネックが復活され、それに伴いローズ指板ネックもネック裏側からトラスロッドが装填され、どちらもネック裏側にスカンクストライプが有ります。ヘッド側からネック調整のアプローチをするブレッドトラスアジャストや3ボルトネックジョイントはマイクロティルト機構の導入によって採用されたと思われ、最小セットアップでの許容範囲が広がりましたが、ネックポケットでのボディとネックは密着度が下がり振動伝達が若干スポイルしたと言え、サウンドにその傾向は表れて線の細い印象です。
1956年中頃からボディは基本的にアルダーですがシースルーのブロンドカラーに関してはアッシュ材が使われてきましたが、1972年頃からナチュラルカラーがバリエーションかされてアッシュボディが使われ始め、その後の74年頃には完全にアッシュ材へ変わります。この時期から再び採用されたアッシュ材は60年代までに使われたスワンプアッシュとは異なり、産地が異なるホワイトアッシュと呼ばれるアッシュ材が使われており、スワンプアッシュと比べて重く、杢も荒い特徴で、70年代後半にかけて更に重みが増す材が使われ、重量増しに合わせて低域が強調される傾向にあります。
エルボー、ウエストコンターは徐々に浅くなり体積増加に合せて70年代後期のモデルは歴代ストラトキャスターに中で最も重く、その重量によって敬遠される傾向にあります。また、ポリエステルによる塗装の下地処理が容易になったことで、ボディの生地段階での仕上げ精度が低下し、更にポリエステルコート部は厚みを増し更なる重量増加の一因でもありました。先に述べたシールドプレートも薄いアルミホイルによるコントロール周辺のみになり、ピックアップのターン数減少による特性と相まってエッジの効いた高音域とボディの音響特性による低域によって70年代の ストラトキャスターサウンド は「ドンシャリ」な傾向と言われています。
1954年の発売から様々なサウンドキャラクター
70年代末までの約25年を振り返っても、ボディ材、指板材や大小さまざまなスペック変更により、各年式による特徴的な ストラトキャスターサウンド を作り出されてきました。ピックアップなどの細かな仕様変更もこれらの変化に作用しているのですが、やはり著者は木工部や塗装が最も大きなファクターであると考えます。これまで説明してきた傾向を踏まえて、ストラトキャスターサウンドを改めて考えることは、本物のヴィンテージストラトを手にしなくてもストラトキャスターの理解を深めることと思います。
Theoneストアのご案内
Theoneストアでは本店、Yahoo店、楽天市場店の3店舗にて運営しています。Yahooと楽天につきましては、各種モールのキャンペーンに参加していますので、お得にポイントをゲットできる日も御座いますので、モールユーザー様は是非ご利用ください。
好評頂いている DYNAX IR に関しましては 本店のみの取扱いとなります。
最新投稿記事
-

アンプシミュレーターIR で音が激変する! DYNAX IR を考察
-

全機種比較| ギターエフェクター 初心者におすすめ エフェクツベーカリー の全て!現役プロが教える選び方のコツ
-

ギターアンプ パワー菅 選び方から交換方法、バイアス調整のことなどプロが徹底解説
-

Strymonエフェクター 定番モデルとサウンド品質を徹底比較!ギタリストにおすすめはこれだ
-

ギターアンプ プリ菅 12AX7 交換で音質激変!理想のサウンドを手に入れる方法
-

新時代の リバーブペダル Strymon BigSky MX
-

RETROLABピックアップ は、最高峰の ストラトピックアップ だと思います!
-

VERTEX SSS ダンブル系プリアンプは 掛けっぱなしが基本!
-

VELVET COMP VLC-1 を modしてみた DYNAX mod
-

Marshallアンプ では 初のコンボアンプ 1962 Bluesbreaker
-

近代Marshallサウンドの方向性を決定づけた JCM800 シリーズのキャビネット1960A
-
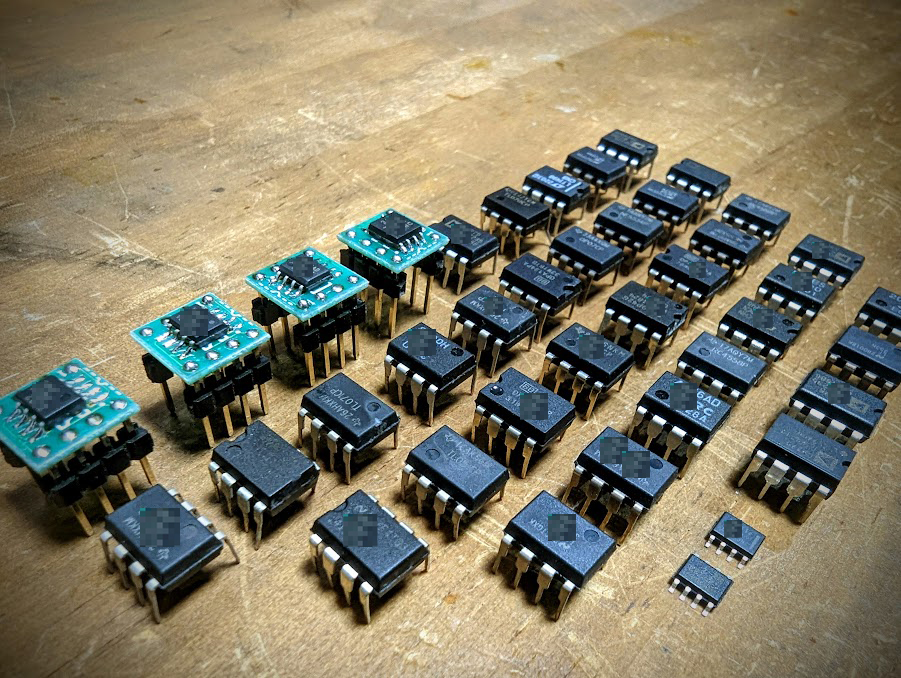
DYNAXオーバードライブ 開発開始しています。
HOME > エレキギター コラム > ストラトキャスターサウンド の特徴を考察 Fender Stratocaster | THEONE | ハイエンド エフェクターなどの解説


